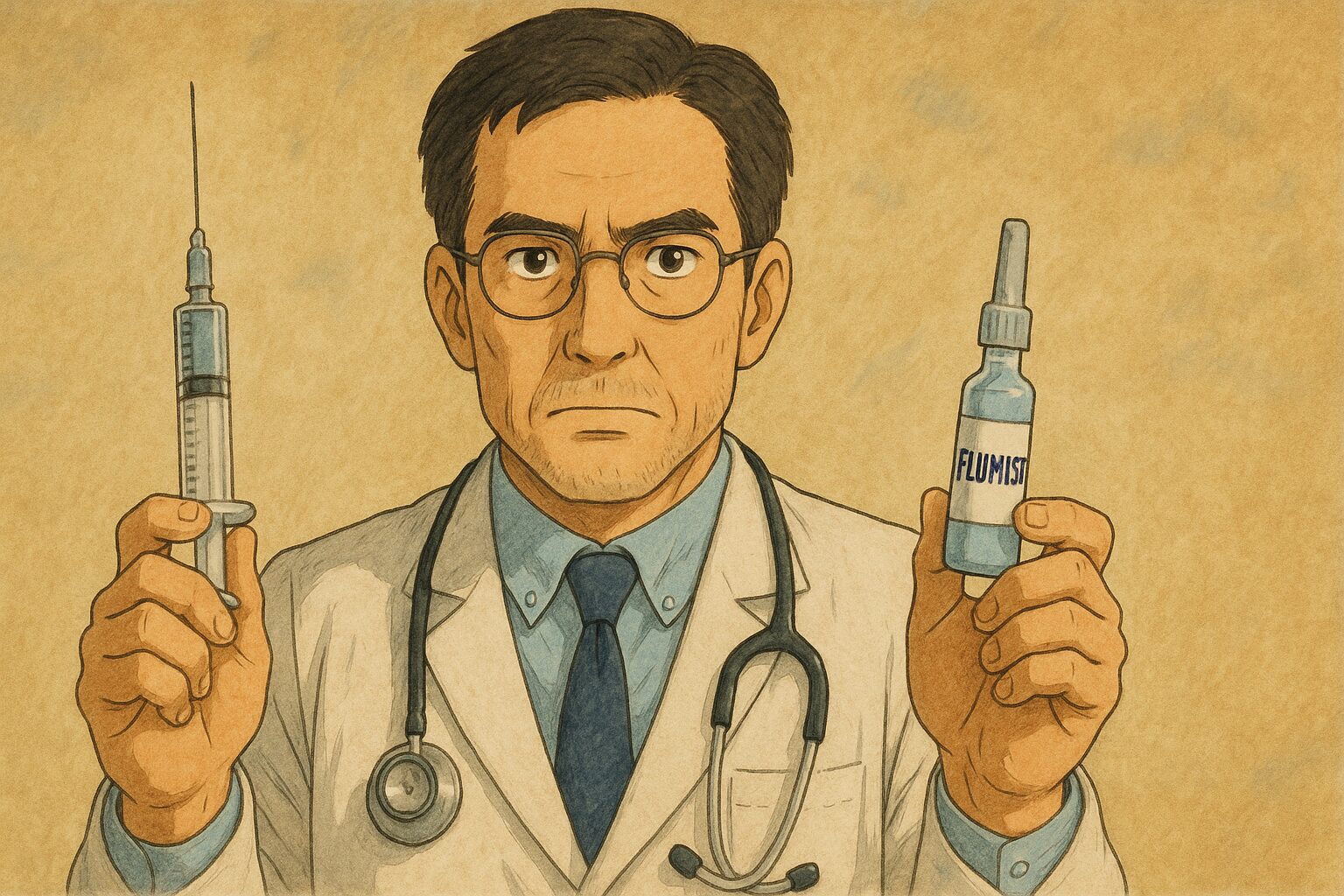はじめに
先日、インフルエンザワクチンの不活化と鼻スプレーの違いについて、わかりやすさ重視で簡単に解説しました↓
とてもシンプルに書いたので、細かなエビデンスなどは省略していますが、その裏には多くの研究がなされています。折角ですので、ご興味を持っていただけた方用に、詳細バージョンもご用意しました。
不活化ワクチン(注射)と生ワクチン(経鼻スプレー)の基本的な違い
インフルエンザワクチンには、大きく分けて注射で接種する不活化ワクチンと、鼻に噴霧して接種する生ワクチン(弱毒生ワクチン)があります。
不活化ワクチンはインフルエンザウイルスを殺して無毒化した成分(主にウイルス表面のHA抗原)を含むワクチンで、体内に入れてもウイルス自体は増殖せず、安全ですが、その分免疫のつき方が穏やかです。
一方、生ワクチン(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン、商品名フルミスト)は病原性を弱めた生きたインフルエンザウイルスを含んでおり、自然の感染に近い形で免疫を誘導することを狙っています。フルミストのウイルスは体内で実際に鼻や喉の粘膜で一時的に増殖し、粘膜でのIgA抗体(鼻や喉の局所免疫)や全身の免疫反応を引き起こします。そのため、上気道(鼻や喉)の入り口でウイルスをブロックする効果が期待できます。
一方、不活化ワクチンは主に血液中にIgG抗体を作り、体内にウイルスが入った際に増殖や重症化を防ぐ効果があります。
両者の接種方法の違いも重要です。不活化ワクチンは筋肉や皮下に注射針で接種しますが、フルミストは鼻にスプレーするだけで接種が完了します。このため、生ワクチンの最大のメリットは痛みがないことです。特に子どもにとって、注射による痛みは大きなストレスですが、鼻からのスプレー型なら痛みや針による恐怖がありません。またフルミストは1回の噴霧で接種が完了するのも特徴です。
フルミストのウイルス株は「コールドアダプト(低温適応)」といって約25℃の低温ではよく増える一方、体温に近い37〜39℃では増えにくい性質に調整されています。そのためウイルスは鼻の中など涼しい粘膜で局所的に増殖しますが、肺のような暖かい場所では増えられず、実際にインフルエンザを発症させることはほとんどありません。
こうした違いから、不活化ワクチンと生ワクチンはいずれもインフルエンザ予防に有効ですが、働き方や接種体験(痛みの有無)が異なります。
接種対象年齢と接種回数の違い
不活化ワクチン(注射型)は原則として生後6か月以上であれば接種可能です。6か月未満の赤ちゃんには安全性・有効性が確認されていないため接種できません。日本では13歳未満の小児は1シーズンに2回接種することが推奨されています。1回目接種より2回接種した方が抗体価(免疫の指標)の上昇が高く、効果が確実になるためです。実際、厚生労働省も「13歳未満の方は2回接種」と定めており、6か月~3歳未満では1回あたり0.25mL、3歳以上13歳未満では1回0.5mLを2回接種するとされています。一方、13歳以上の人は1回接種が原則です。
健康な成人では0.5mLを1回打つだけで2回と同等の抗体上昇が得られるとの研究報告があり、現在日本では13歳以上は通常1回接種としています。(医師が必要と判断する場合は2回接種することもあります。)
生ワクチン(フルミスト)は接種できる年齢が限定されています。日本で承認されたフルミストの適応は満2歳~18歳(19歳未満)で、それ以外の年齢には原則使用できません。これは、生ワクチン特有の安全性上の理由から定められています。特に2歳未満の幼児については、臨床試験で接種後に喘鳴(ぜんめい:呼吸がゼーゼーする症状)や入院のリスク増加が見られたため使用が許可されておらず、必ず不活化ワクチン(注射)を使います。また妊婦や重い免疫不全の方、重度の喘息など慢性疾患がある方もフルミストは避け、不活化ワクチンで予防することになっています。
フルミストの接種回数は年1回です。1シーズンに1回の鼻噴霧で完了し、追加接種は不要とされています。日本の基準でも2歳~18歳では1回の接種で十分な効果が得られると考えられています。量は両側の鼻に0.1mLずつ(計0.2mL)噴霧し、子どもでも苦痛なく素早く終わります。なお、フルミストも他のインフルエンザワクチンと同様に毎年接種する必要があります。インフルエンザウイルスは毎年流行株が変異するため、ワクチンも毎年最新株に合わせて作られます。したがって一度接種しても翌年以降には効果が持続しないので、シーズンごとに接種が推奨されます。
ワクチンの有効性(年齢による効果の違い)
インフルエンザワクチンの有効性は、接種した人がインフルエンザにかかるのをどれだけ防げるかという指標で、年齢やそのシーズンの流行株とのマッチ具合によって異なります。不活化ワクチンも生ワクチン(フルミスト)も、総じてインフルエンザ発症リスクを下げ、重症化を予防する効果があります。
現時点で、子どもにおいて両者の「発症予防効果に明確な優劣はない」とする報告もあり、基本的にはどちらも有効と考えられます。例えば日本小児科学会も「2~18歳では不活化ワクチンと生ワクチンのいずれかで予防することを同等に推奨する」としています。実際、日本で行われた臨床試験でもフルミストを接種した子ども達はしない子に比べてインフルエンザ発症が約3割減少しており、ワクチンの有効性が示されています。
一方、不活化ワクチンも毎年の分析で概ね50%前後の発症リスク減少効果が報告されており(年によって差はあります)、双方とも一定の予防効果を発揮します。
年齢による効果の差を見ると、小児(2~18歳)に対してはフルミストの有効性が特に高いことを示す研究があります。生ワクチンは自然感染に近い総合的な免疫を誘導しやすいため、小児では注射より高い予防効果を示したとの報告もあります。
例えば海外の分析では、フルミストは従来の注射と同等かそれ以上の効果を示し、特に子どもでは注射より有効性が高かったという結果が得られています。また、生ワクチンは鼻の粘膜からの免疫で感染そのものを防ぐ力も期待できるため、子どもがインフルエンザにかかって周囲へうつすのを減らす効果(集団予防効果)も見込まれています。
ただし、生ワクチンは年によって一部の株で効果が十分発揮できなかった例もあり、かつて米国ではあるシーズンに一時的にフルミストの推奨が中止されたこともあります(※この問題はワクチン株の改良により解決しています)。
総合的には現在、小児ではフルミストも注射もいずれもしっかり予防効果があるという認識で良いでしょう。
一方、成人や高齢者に目を向けると、生ワクチンの有効性はやや異なります。成人(特に若年成人以降)ではフルミストの効果が注射より劣る可能性が指摘されています。
これは年齢が上がるにつれて鼻の粘膜免疫の反応が弱くなるため、生ワクチンを鼻から投与しても十分な免疫がつきにくいことが一因と考えられます。実際、高齢者では注射ワクチンの方が確実とされ、海外でもフルミストは50歳以上には使用されていません(米国での適応は2~49歳まで)。
高齢者の場合、従来の不活化ワクチンでも効果が落ちる傾向があるため、海外では高齢者向けに抗原量を増やしたワクチンや添加剤(アジュバント)入りワクチンが使われることもあります。それほど年齢によってワクチン効果は左右されるのです。
まとめると、2~18歳の小児・若年層ではフルミストが痛みのなさと同時に十分な効果を発揮しうる一方、乳幼児や高齢者には不活化ワクチンでカバーする必要があるといえます。
副反応・安全性の違い
インフルエンザワクチンはどちらのタイプも安全性が確立されており、大きな副反応(副作用)は稀ですが、それぞれ特有の反応があります。
まず不活化ワクチン(注射)の副反応ですが、主なものは接種部位の痛み・腫れ・赤みです。接種を受けた人の約10~20%で腕の注射箇所が赤くなったり腫れたり痛んだりしますが、通常2~3日で治まります。また5~10%程度の人に発熱や寒気、頭痛、全身のだるさなど全身症状が一時的に出ることがありますが、こちらも2~3日以内に消失する軽いものです。極めてまれにアナフィラキシー(重度のアレルギー反応)などの重篤な副反応が起こることがありますが、その頻度は100万回に1回未満と報告されており非常に低いものです。
一般的にインフルエンザ注射で重大な副作用が起こることはほとんどなく、安心して接種できるワクチンです。なお、かつてインフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群という神経の病気がごく稀に発症する関連が指摘されたことがありますが、因果関係は明確でなく頻度も極めて低いとされています。
総じて、注射型ワクチンは副反応が少なく安全ですが、接種時の痛みや腫れは避けられない点がデメリットと言えます。
次に生ワクチン(フルミスト)の副反応・安全性です。フルミストは注射と比べて接種時の痛みがない反面、接種後に鼻や喉の軽い症状が出ることがあります。
具体的には、約半数の人に鼻水や鼻づまりが見られるとの報告があります。また咳が出る人が2~3割、微熱が出る人が1割未満いるとされています。これらはいずれも軽微な症状で、出ても数日中に自然に治まり、重症化するようなものではありません。まれにじんましん等のアレルギー症状や喘息様の症状が出ることがありますが、頻度が他のワクチンに比べて特別高いわけではありません。注射と同様にアナフィラキシーなど重篤な反応も極めてまれですが起こり得るため、接種後しばらくは医療機関で経過を見るなど安全措置が取られます。
フルミストは生きたウイルスを使うため、接種できない人・注意が必要な人が定められています。重い免疫不全のある人や免疫を抑える治療中の人、先天的に無脾(脾臓がない)など免疫弱者、慢性の呼吸器疾患や心疾患で状態が悪い人、重度の喘息患者、そして妊婦にはフルミストは使用せず注射ワクチンを使うことが推奨されています。
また、2歳未満の乳幼児も前述の通りフルミストは禁忌です。
アスピリンを長期服用中の子どもも、生ワクチン接種後にまれにライ症候群という肝臓の重い病気を起こすリスクが指摘されているため避けます。卵アレルギーについては、フルミストも製造に鶏卵を使用しているため、卵を食べて症状が出るような重度の卵アレルギーの方は注意が必要です(ただし卵アレルギーでも接種自体は可能であり、重症例では医師の監督下で慎重に接種します)。
フルミスト接種後は、ワクチンウイルスが周囲にうつる可能性にも注意します。フルミストの弱毒ウイルスは接種後1~2週間程度、鼻水やくしゃみなどを通じてごくまれに他の人へ移ることがあると報告されています。健康な人に広がっても軽い鼻風邪程度の症状しか起こしませんが、問題は周囲に重度の免疫不全の方や乳児がいる場合です。そのような場合は、フルミスト接種後約2週間は接触を避けるかマスクの着用を徹底するなど配慮が必要とされています。(極端に免疫の落ちた人が身近にいる場合は、家族もフルミストではなく注射で予防する方が無難でしょう。)
以上のように、生ワクチンは一部の人には使えない制限がありますが、適応となる健康な子ども達にとっては安全性は高く、副反応も一時的な鼻風邪症状程度で済むことがほとんどです。
1歳未満で不活化ワクチンの効果が弱いと言われる理由
インフルエンザ不活化ワクチンは生後6か月から接種できますが、1歳未満の赤ちゃんでは「効果があまり高くない」と言われています。
その科学的な理由としては、赤ちゃん側の要因とワクチン側の要因の両方があります。まず赤ちゃん側として、生後間もない乳児は免疫システムが未熟でワクチンに対する反応が弱いことが挙げられます。
また生後6か月くらいまでは母親から胎盤を通じてもらった移行抗体が残っており、ワクチン抗原に対する反応を妨げてしまう可能性もあります。
このため「まだ一度もインフルエンザに罹ったことのない赤ちゃんには、ワクチンで免疫をつける力が弱い」と実感されるのです。実際、1歳未満で接種しても予防効果は20〜25%程度(接種しない場合と比べて感染リスクが2割程度減る)と報告されており、かなりの赤ちゃんが接種してもインフルエンザにかかってしまうのが現状です。
しかし一度も効果がないわけではなく約2割は予防できること、さらに1度接種を経験しておくと翌年以降のワクチン効果が上がりやすくなる(免疫の下地ができる)こともわかっています。そのため、特に集団生活をしていたり感染リスクの高い赤ちゃんについては「効果は限定的でも接種しておいた方がよい」という意見もあります。
ワクチン側の要因としては、赤ちゃんに対する接種量の問題があります。日本では2011年から乳幼児のインフルエンザワクチン量が見直され、生後6か月~3歳未満は1回0.25mLに増量されました(以前は0.1mL×2回でした)。これは、過去の研究で乳児は接種量が少ないと抗体反応が十分に上がらないことが示されたためです。実際、ある研究では0歳児(当時0.1mL接種)と1歳児(0.2mL接種)の抗体価上昇を比較したところ、年齢差ではなくワクチン接種量の差が抗体反応の差を生んでいたと報告されています。つまり乳児には現行の少ない接種量では十分な免疫をつけるのが難しく、「乳児にも0.2mL(現在の0.25mL相当)に増量すべきだ」と指摘されました。この提言を受け、先述の通り現在では乳児でも0.25mL接種していますが、それでも幼い乳児では十分な抗体ができにくいという課題が残ります。
まとめると、1歳未満ではワクチンを打っても効果が出にくいのは、ワクチン成分量の制約と赤ちゃんの免疫の未発達によるものです。ただし繰り返しになりますが、まったく効果がないわけではなく一定の予防効果と将来への免疫の下地作りには役立ちます。
このため、生後6か月~1歳の接種は「必ずしも推奨されない」が「状況によっては接種を検討してよい」という扱いになっており、家庭内や保育園などでの感染リスクの高さによって医師と相談して決めると良いでしょう。ちなみに生後6か月未満の赤ちゃんは前述の通りワクチン適応外のため接種できませんので、周囲の大人が予防接種を受ける「コクーン戦略(繭戦略)」で赤ちゃんを守ることが大切です。
フルミストの日本における導入状況・承認範囲
鼻スプレー型インフルエンザ生ワクチン「フルミスト」は、海外では以前から使用されていましたが、日本では長らく未承認の状態が続いていました。アメリカでは2003年に初承認・使用開始され、ヨーロッパ諸国でも2011年以降広く使われています。
日本でも小児科領域でその有用性が期待され続けましたが、米国で一時期効果に疑問が持たれ推奨から外された経緯もあり(特定のシーズンで効果不十分と判断されたため)、導入が遅れていました。転機となったのは近年の研究データの蓄積で、有効性・安全性が再確認されたことです。
それを受けて2023年3月27日、日本でフルミスト(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン)がついに製造販売承認されました。そして2024/25年シーズンから実際に国内の医療機関で接種が開始されています。つまり2024年の秋冬シーズンから、日本の子ども達も痛くないインフルエンザワクチンを受けられるようになったわけです。
現在フルミストは生後2歳~18歳未満を対象に、日本全国の希望する医療機関で接種可能です。任意接種(公費負担なしの自費)扱いであり、費用は1回あたり約7,000~9,000円程度と設定している施設が多いようですが、1回で済むため2回接種の注射と大きく費用が変わらない場合もあります。
フルミストが承認された背景には、「子どもの予防接種体験をより良いものにしたい」という思いがあります。日本小児科学会も「小児にとってワクチンの痛みは重大な懸念事項であり、経鼻接種による痛みの軽減は重要な意義がある」とコメントしています。痛みがないことでワクチン嫌いにならず、スムーズに予防接種が受けられるメリットは計り知れません。また1回で完了することで保護者の負担も減り、接種漏れを防ぐことにもつながります。
もちろん注射の不活化ワクチンも従来から多くの命を守ってきた有効な手段であり、今後も6か月~2歳未満の乳幼児や基礎疾患のある方、高齢者などには不可欠です。
一方で2歳以上の健康な子どもにはフルミストという新たな選択肢が加わったことで、インフルエンザ予防のアプローチがより多様になりました。両ワクチンの効果自体に大きな差はなく双方とも有効ですが、「痛くない」「1回で済む」フルミストのメリットは子育て世代にとって魅力的です。
今後、日本におけるフルミストの普及が進めば、子ども達の笑顔で受けられる予防接種が増え、インフルエンザの流行防止にも一層寄与することでしょう。ママさん・パパさんも、本記事の情報を参考に、ぜひ小児科の先生と相談しながらお子さんに合ったワクチン方法を選んでみてください。
インフルエンザワクチンはどちらのタイプであっても毎年欠かさず受けることが大切ですので、痛みや回数の不安がある場合は遠慮なく医療者に相談しましょう。お子さんにとってベストな形でインフルエンザ予防ができますように。