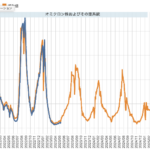あらすじ
今日は「マダニに気をつけましょう」というテーマ。
最近よく耳にする「マダニ感染症」、その中でも話題のSFTS(重症熱性血小板減少症候群)を含めて、
- なぜ今注目されてるの?
- マダニってどんな生き物?
- かまれるとどんな病気が心配?
- SFTSってどんな病気?
- 日常でできる予防や、もしもの時の対応
をわかりやすくまとめました。
公園やキャンプ、お子さんとのお散歩も安心して楽しめるように、一緒に学んでいきましょう!
今なぜマダニが注目されている?
ここ10年ほどで、日本各地でマダニが媒介する新しい感染症が見つかってきました。
- 2013年に国内で初めて報告された「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」
- 2021年、北海道で確認された「エゾウイルス」
- 2023年には茨城県で「オズウイルス」
どれも人に深刻な症状を起こす可能性があるため、厚労省や自治体も「マダニに注意!」と呼びかけています。
さらに気候変動や野生動物の動きで、マダニの分布が広がっていることも注目される理由のひとつです。
マダニってどんな生き物?
マダニは「クモの仲間」で、肉眼でも見えるサイズの吸血生物です。
- 普段は数ミリですが、血を吸うと1cm以上に膨れ上がることも。
- 日本には40種類以上のマダニが生息し、人やペットに吸着する種類も多いです。
- 幼虫 → 若虫 → 成虫と、成長のたびに吸血が必要で、その際に病原体を媒介することがあります。
マダニに噛まれるとどういう病気が心配?
- SFTS(重症熱性血小板減少症候群):致死率が高く、発熱や出血傾向を伴う感染症。
- エゾウイルス感染症・オズウイルス感染症:比較的新しい報告。研究が進行中。
- ツツガムシ病・日本紅斑熱:昔から日本で報告されるダニ媒介感染症。年間数百例あり。
今話題の重症熱性血小板減少症候群とは?
症状
- 発熱・強い倦怠感
- 吐き気・下痢・腹痛などの消化器症状
- リンパ節の腫れ、出血傾向、意識障害など重症化するケースも
- 致死率は10〜30%とされ、特に高齢者や基礎疾患のある方は注意が必要
診断
- 「マダニに刺された」という情報が重要な手がかり
- 血液検査で血小板や白血球の減少、肝機能の異常を確認
- PCR検査でウイルスの遺伝子を検出、または抗体検査で診断が確定
治療
- 特効薬はまだ確立していません
- 点滴・解熱・輸血などの対症療法が基本
- 抗ウイルス薬「ファビピラビル(アビガン)」は研究段階で、臨床試験も進められています
- 重症例は集中治療室での管理が必要になることもあります
マダニってどこにいるの?
- 森林や草むらだけじゃなく、公園・庭先・畑のあぜ道にも!
- ペットや野鳥が運んでくるため住宅街でも油断できません
- 春〜秋に活発ですが、冬でも活動する種類がいます
我が子や動物も危険?どう気をつける?
服装でしっかりガード
長袖・長ズボン、明るい色で露出を減らしましょう。裾や袖を靴下・手袋に入れるとさらに安心。
虫よけ剤を活用
ディートやイカリジン入りの市販スプレーは一定の効果あり。
海外では靴や服に「ペルメトリン処理」をして防御力を高める工夫もあります。
帰宅後のチェック
シャワーや入浴で体を確認。頭皮や耳の裏、わきの下、足の付け根は特に要チェック!
衣類は高温乾燥で駆除ができます。
万が一かまれたら?
- 無理に取らず、ピンセットで皮膚に近い部分をつかんでゆっくり引き抜く
- 不安なら医療機関で処置を受ける
- その後1〜2週間は発熱・だるさ・発疹に注意。症状が出たらすぐ受診
本日のまとめ
マダニはちょっと怖いニュースと一緒に語られることが多いけれど、正しく知って、正しく予防すれば怖がりすぎなくて大丈夫!
SFTSをはじめとする感染症も、早めに「おかしいな」と気づいて受診することが命を守ります。
公園もキャンプも、お子さんと楽しい時間を過ごすチャンス。ほんの少しの工夫と注意で、その安心はグッと高まります。
がんばるママ・パパを応援しています!